 カウンセラーを探す
使い方
よくある質問
カウンセラーを探す
使い方
よくある質問
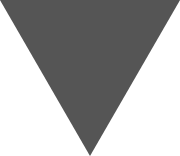

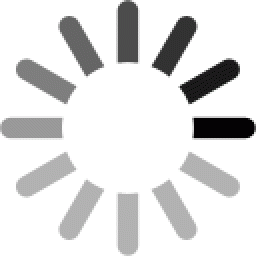


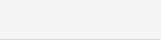
ボトルボイス編集部です。
この時期、ベートーベンの交響曲第九番、喜びの歌を
いろいろなところで聴き、年末を感じる事も多いですね。
ベートーベンの数ある楽曲の中で、なぜこれほどまでに
この交響曲第九番、喜びの歌は人の心に感動を生み出すのでしょうか。
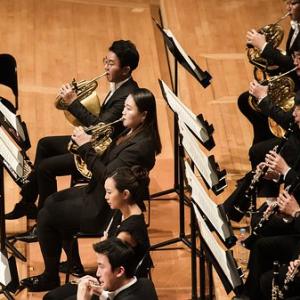
このベートーベンの交響曲第九番、
有名な「喜びの歌」は第四楽章ですが、
他の三楽章については聞いたことがない、
覚えていないという方も多いのではないでしょうか。
交響曲第九番では、第三楽章までは従来のクラシック音楽の
集大成のような形式で作曲されていますが、
第四楽章では、
「このような音楽ではなく、もっと楽しい喜びに満ちた歌を歌おう」
というソロの歌唱から始まり、あの有名な喜びの歌の合唱へとつながります。
クラシックの楽聖と言われ、多くの感動的な曲目を作曲してきたベートーベンが、
最後の交響曲の最後の楽章で人の声を取り入れたというのは、
人の声が持つパワーを改めて感じさせるエピソードですね。
年末の風物詩である喜びの歌を聴いた時、
人の声が生み出す感動の力を思い出してみてください。
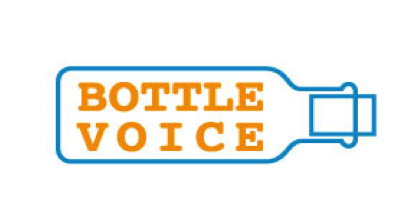
ボトルボイス編集部